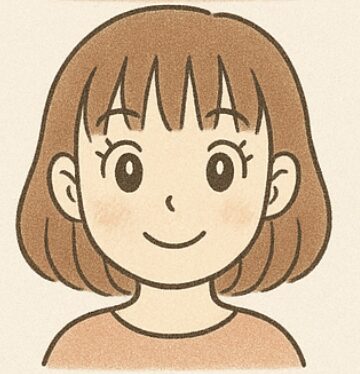
障害のある二児の母🌿普通の専業主婦がパパの1年間の育休を機会に「これからどう生きたい?」を夫婦で深く考えるようになり、個人事業主になりました。
このブログでは、ママ目線での障害児と暮らす家族の変化、本当に大切にしたい価値観などを発信しています。
【導入】両学長の教えを実践!妻の医療保険を解約したけれど…
「日本の公的保険は最強。民間の医療保険はほとんど不要」
資産形成に関心のある方なら、リベ大の両学長がこう発信しているのを聞いたことがあると思います。私もその教えに納得し、家計改善のために医療保険を思い切って解約しました。
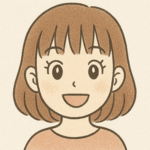 ミライママ
ミライママこれで毎月の固定費が浮いた!資産形成スピードアップだね!
そう喜んだのも束の間。なんとその直後、妊娠が判明し、さらに「切迫早産」により4ヶ月もの長期入院をすることになってしまったのです。
【悲劇】まさかのタイミングで長期入院。頭をよぎる「解約」の二文字





え、保険解約したばっかりなんだけど…
入院が決まった時、真っ先に頭に浮かんだのは体調への心配、そして次に「お金」への恐怖でした。
切迫早産での入院は、安静を保つための長い戦いです。今回は24週で入院となったため、なんと4ヶ月間に渡ります。 治療費、食事代…。
もし保険に入っていれば、給付金でプラスになった。でも、解約してしまったから請求額は自己負担。
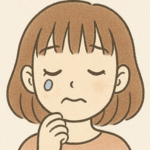
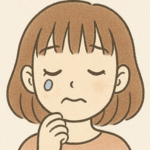
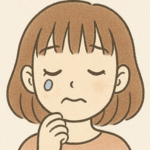
やっちゃった…
1ヶ月目の請求額が届き、正直、冷や汗が止まりませんでした。
なぜあの時、妻の医療保険解約を止めなかったんだ…。 切迫早産で高額療養費適用後も高額請求を見て、心臓が凍る。
— ユウキ@育休で人生変わった。 (@ikukyuu_restart) October 7, 2025
「妊娠が分かったら保険に入れない」からこそ、出産の可能性のある女性は解約はよく考えて。私たち夫婦の失敗談を教訓にしてもらえたら🙏#切迫早産入院 #帝王切開 #長期入院 pic.twitter.com/ALw8dq76rw
2ヶ月目も216,677円の請求が届きます。
妻が切迫早産で4ヶ月の入院予定。
— ユウキ@育休で人生変わった。 (@ikukyuu_restart) October 8, 2025
2ヶ月目の請求も届いた…💦
高額療養費を使っても、自己負担はまだまだ大きい。
保険を解約する判断って「節約」だけじゃなく、心の安心も含めて考えないと、とさらに痛感中。#切迫早産 #高額療養費 #保険 #家計管理 pic.twitter.com/hZ9XD7DhAI
【救い】それでも破産しなかった理由。「高額療養費制度」の凄さ
妻が切迫早産で4ヶ月入院。
— ユウキ@育休で人生変わった。 (@ikukyuu_restart) December 12, 2025
医療費の請求を見たら
「3ヶ月目=0円」「4ヶ月目=188,662円」。
なんで?と思ったら、
出産育児一時金の余りが、前月の入院費に充当されてた。
出産育児一時金の“前月補填”があるとは知らなかった。
出産一時金 > 出産費用 のときは、こういう使われ方するんだね。 pic.twitter.com/R4wpm8RSPC
1ヶ月目 203,006円
2ヶ月目 216,677円
3ヶ月目 0円
4ヶ月目 188,662円
合計 608,345円
結論から言うと、保険を解約していても我が家は破産しませんでしたし、想定外の借金を背負うこともありませんでした。
私たちを救ってくれたのは、日本の最強のセーフティネット、以下の2つです。
- 高額療養費制度
- 出産育児一時金
どんなに医療費がかかっても、高額療養費制度のおかげで、一般的な収入の家庭であれば、年収にもよりますが、月の支払いは約8万円〜(+食事代など)に抑えられます。さらに、出産時にはまとまった一時金も支給されます。



今回は帝王切開だったから適用できたけど、通常分娩の方は、出産費用は「保険診療ではない=自費」扱いのため、高額療養費制度の対象外 になります。
結果として、「保険を解約して大失敗だったか?」と問われれば、「金銭的なダメージは、貯金でカバーできる範囲だった(致命傷ではなかった)」というのが事実です。
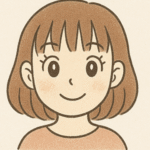
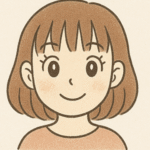
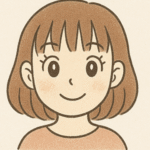
やっぱり両学長の言う通り、公的保険だけでなんとかなるじゃん・・・
一瞬はそう思いました。しかし、入院生活を経て、私の考えは少し変わりました。
【懸念】この「最強の制度」は、いつまで続くのか?
高額療養費制度の改悪問題は、あくまでも先送り状態です。財務省は諦めていませんし、公約に掲げている政党もあります。国民の生きる権利、健康を守る権利は絶対に手放してはいけません。 https://t.co/kBhOGF48pE pic.twitter.com/sldtuJTfuL
— FORCEPS (@FORCEPS4) August 26, 2025
今回の入院で痛感したのは、「今の制度」のありがたさと同時に、「将来への不安」です。
少子高齢化が進む日本において、現役世代の負担は年々増しています。 ニュースを見れば、「医療費の窓口負担増」や「社会保険料の引き上げ」の話題ばかり。
- 高額療養費制度の自己負担限度額が、今後引き上げられるかもしれない。
- 公的保障の範囲が縮小されるかもしれない。
「今」は公的保険だけで大丈夫でも、10年後、20年後に私たちが病気になった時、同じように国が守ってくれる保証はどこにもありません。
貯金が十分にあれば問題ありませんが、もし公的制度が改悪された時、手持ちの現金だけで全ての医療リスクに対応できるだろうか? そんな不安が、入院生活を通して頭をよぎりました。
【結論】「不要」ではなく「最低限」のお守りは必要かもしれない
今回の経験から導き出した、我が家の新しい結論。 それは、「過度な保険は不要だが、最低限の備えは持っておくべき」ということです。
公的制度が改悪されるリスクへのヘッジとして、そして長期入院時の精神的な安定剤として、掛け捨てで負担の少ない「最低限の医療保険」に入っておくことは、決して無駄遣いではないと感じています。
もちろん、両学長が警鐘を鳴らすような「ぼったくり保険」や「貯蓄型保険」は論外です。 選ぶなら、「掛け金が安く、必要な保障だけがついているシンプルな保険」一択です。
【推奨】おすすめの医療保険
では、具体的にどの保険なら「入ってもいい」と言えるのか?
コストパフォーマンスに優れた「最低限の備え」としておすすめなのがこちらです。
- FWD生命(FWD医療):シンプルで保険料が安いのが特徴。
- メディケア生命:必要な特約だけを選びやすい。
- 県民共済:やはりコスパ最強。割戻金もあるため実質負担はさらに軽い。
※ご自身の年齢や家族構成に合わせて、シミュレーションしてみてください。
なぜこの3社なのか?
選定基準
- 「掛け捨て」かつ「低廉」であること
- 貯蓄型などの余計な手数料が乗った商品は除外。純粋にリスクヘッジだけを買える。
- 保障内容がシンプルであること
- 約款が複雑怪奇ではなく、必要な時に必要な分だけ出るわかりやすさがある。
- ネット申し込み(または簡易手続き)が可能であること
- 人件費(代理店手数料)がカットされており、保険料に還元されている。
【保存版】あなたに合うのはどれ?タイプ別・医療保険比較表
| 特徴 / 保険会社 | ① FWD生命(FWD医療) | ② メディケア生命(新メディフィットA) | ③ 都道府県民共済(総合保障型など) |
| こんな人におすすめ | とにかく毎月の固定費を 最安値に抑えたい人 | 女性特有の病気や自分好みに保障を足したい人 | 年齢が若く、 とりあえずの繋ぎで入りたい人 |
| 保険料の安さ | ◎ 業界最安水準 | ◯ 十分安い | ◎ 安いが、年齢で上がらない (一律掛金) |
| 一生涯の保障 | あり(終身医療保険) | あり(終身医療保険) | なし(65歳〜85歳等で終了・減額) |
| カスタマイズ性 | △ シンプルイズベスト | ◎ 特約が豊富で優秀 | ✕ パッケージ型で選べない |
| 割戻金 (実質値引き) | なし | なし | あり(毎年一部返ってくる) |
| リベ大・通説的評価 | 「最低限のお守り」。 | コスパと保障のバランスが良い。女性特有のリスクに強い。 | コスパ最強だが、 老後の保障が弱点。 |
| 公式サイトへ | [FWD生命を見る] | [メディケア生命を見る] | [共済を見る] |
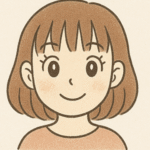
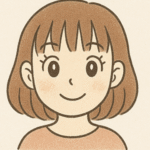
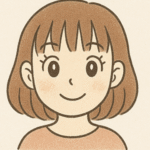
様々な状況によって、あなたに合う保険は変わるかもしれません。
保険見直しラボなら、上記2社を含む、優良な保険の見直しの相談に無料で乗ってくれます。気になる方はどうぞ。
まとめ


- 公的保険(高額療養費制度)は確かに最強で、今回の長期入院もそれで乗り切れた。
- しかし、日本の社会保障制度が今後も今の水準を維持できるかは不透明。
- 将来のリスクヘッジとして、「家計を圧迫しない最低限の掛け捨て保険」に入るのは賢い選択。
「保険は全くいらない!」と極端になるのではなく、「制度の限界」を見据えた上で、最低限の保険を利用する。これが、切迫早産を乗り越えたわが家のリアルな結論です。



高額の医療費がかかったので、年明けに確定申告し医療費控除にチャレンジしようと思っています。また、どれくらい戻ってくるのかなど情報提供できたらと思います。
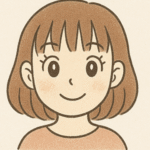
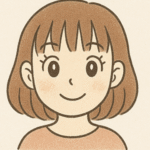
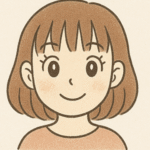
医療保険の見直しについて、皆さんのご家庭の参考になれば幸いです。

コメント